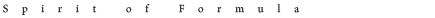
フォーミュラの魂 2011 “第2戦 オートポリス”

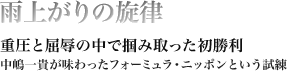
第2戦オートポリスでの戦いが終わった。表彰台の上に高く掲げられる日の丸。流れる君が代。彼は、その旋律を目を閉じ、耳を澄まして聞いていた。心に深く染み入る音色。表彰台の一番高い場所で、このメロディーを聞くのは、5年ぶりのこと。厚い雲が切れ、そこから射し込む夕陽が、中嶋一貴の顔を明るく照らしていた。
屈辱の連続Q1脱落
“元F1ドライバー”中嶋一貴は期待の星。勝って当たり前といわれていた。だが、そこは常に僅差の戦いを強いられるフォーミュラ・ニッポン。わずか2戦で、彼はとんでもない屈辱を味わうことになる。
第2戦の予選。一貴は、(一度走行した)ユーズドタイヤでマシンバランスを確認した後、(グリップ力の高い)ニュータイヤを装着。アウトラップ(ピットを出た1周)を終えると、すぐタイムアタックに入る。これがオートポリスではセオリー。ここの路面は、タイヤへの攻撃性が高い。他のサーキットのように、アウトラップの後、調子を整えようと1周してアタックに入れば、その時点ですでにタイヤのグリップはドロップダウンしているのだ。
 当然、一貴も、アウトラップを終えると即、アタックに入る。ところが、第2ヘアピンの入り口でリヤタイヤをロック。シフトダウンができず、一旦スローダウンすると、次の周に仕切り直してのアタックに入った。その1周を終えて、計測ラインを通過した一貴。だが、結果は13番手。開幕戦に続き、連続のQ1敗退だった、
当然、一貴も、アウトラップを終えると即、アタックに入る。ところが、第2ヘアピンの入り口でリヤタイヤをロック。シフトダウンができず、一旦スローダウンすると、次の周に仕切り直してのアタックに入った。その1周を終えて、計測ラインを通過した一貴。だが、結果は13番手。開幕戦に続き、連続のQ1敗退だった、
「無線から何も聞こえてこなかったので、ダメだったのかなと思いましたが、ダメだと分かった時には、確かにへこみましたね。でも、そのポジションから、レースでは何とかしなくちゃと思って、作戦を考えました」
難しいミッションを着々とこなす
それを実行するためにも、日曜日朝に行われるフリー走行では、ドライコンディションの中でのマシンのバランスを確認したかったが、外は生憎の雨。希望通りのスケジュールで、プログラムを消化することはできなかった。
そのまま臨んだ決勝レース。路面はセミウェット。だが、雨はパラついている程度で、乾いて行く方向と思われた。
「8分間のウォームアップ(暖気のための走行)やグリッド(決勝前のスタート位置)ではまだ雨が降っていましたが、フォーメーションラップを走っている時に、これならスリックでも行けそうだと思いました。それで、1周目に入ることをチームと相談して決めたんです」
決勝レースのスタートが切られると、その通り、一貴は1周を終えてすぐさまピットイン。他チームが判断に迷う中、スリックでプッシュし、序盤の段階でいきなり2位まで進出する。そこからは難しいミッションが待っていたが、それを着々と実行していった。
「自分が他のドライバーよりもタイヤに優しい(運転ができる)と信じて走っていました。燃費に関しても、チームに確認しながら。そうしたら、どこかの段階で、これで(最後まで無給油で)走り切れると言われました」
前を行くのはTDP(トヨタ・ヤングドライバー・プログラム/若手支援のスカラーシップ)の後輩であり、フォーミュラ・ニッポンですでに1勝をしている大嶋和也。あとは彼をとらえるのみ。一貴は無理に差を詰めることなく、大嶋の動きを観察していた。次第にキツそうになってくるその走りを見抜いていたのだ。
 そして、54周のレースが残り13周を切った42周目の1コーナー。一貴は、躊躇なく勝負を賭ける。オーバーテイクシステムのボタンが押されると、ミントグリーン/ホワイトのマシンはライトを点滅させながら、エンジンをパワーアップ。青と白に彩られた大嶋のマシンをアウトから力強く追い抜いていった。初めてトップに立った瞬間だった。
そして、54周のレースが残り13周を切った42周目の1コーナー。一貴は、躊躇なく勝負を賭ける。オーバーテイクシステムのボタンが押されると、ミントグリーン/ホワイトのマシンはライトを点滅させながら、エンジンをパワーアップ。青と白に彩られた大嶋のマシンをアウトから力強く追い抜いていった。初めてトップに立った瞬間だった。
そこからは自分のクルマ、タイヤと対話しながらの走り。一貴は、完全にレースをコントロールしていた。
心にしみた“君が代”
トップチェッカーを受けると、ようやく一貴の気持ちは解放される。1コーナーでは残念ながらリタイヤしてしまった弟の大祐が、こちらに向かって拍手しているのが見えた。胸が熱くなった。そこからの1周、一貴は『オレが1番だ!』というように人差し指1本を立て、時にはガッツポーズしながら走った。
「F1をテレビで見ていて、セバスチャン・ベッテルが勝った時に、1周ずっと指を立てているのを見て、ウザイっていう人もいますけど、今日はセバスチャンの気持ちが、本当によく分かりました。僕もこれから、F1で彼のウィニングランを見て、ウザイって思わないようにしますよ」
そう言うと、笑顔を見せた一貴だったが、表彰台では思うところが多くあった。
「あの君が代は、すごくしみましたね…」
海外に旅立ってからの数々の苦労。悔しさ。帰国してからの“勝って当然”という雰囲気。そのすべてを振り払って、一貴はようやく表彰台の一番高い場所に戻ってきた。

Reported by Yumiko Kaijima



