Headline News
第4回CN開発テスト インサイドレポート
2022年6月23日
サッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING)の初優勝で幕を閉じた全日本スーパーフォーミュラ選手権・第5戦。その興奮も冷めやらぬ6月20日(月)〜21日(火)の2日間、宮城県・スポーツランドSUGOでは「SUPER FROMULA NEXT50」プロジェクトの柱の一つ「カーボンニュートラルの実現に向けた素材・タイヤ・燃料の実験」、「ドライバーの力が最大限引き出せるエアロダイナミクスの改善」を目的とした開発テストの4回目が行われた。
レースウィークと同様、すでに梅雨入りは発表されたものの、宮城県地方は好天に恵まれ、テスト初日となった20日も、朝から真夏のような陽射しが降り注ぐ。湿度もかなり高く、蒸し暑いコンディションの中でのテストとなった。持ち回りとなる車両のメインテナンスは、ホンダエンジン搭載のホワイトタイガーSF19 CNを今回B-Max Racing Teamが担当。トヨタエンジン搭載のレッドタイガーSF19 CNをP.MU/CERUMO・INGINGが担当。JRPの上野禎久社長や永井洋治テクニカル・ディレクター、土屋武士アンバサダー、さらにTRDやHRC、横浜ゴムのエンジニアたちが見守る中、今回も塚越広大、石浦宏明の2人が精力的に周回を重ねた。

テスト初日、最初のセッションが行われたのは午前10時から午前12時の2時間。朝から照りつけた陽射しによって、セッション開始時の気温はすでに28℃まで上昇。路面温度も39℃となっていた。そこからセッションが進むにつれて、さらに上昇。2時間のセッション最後には、気温が30℃、路面温度が49℃と、レースウィーク以上の暑さとなっている。
このセッションでは、横浜ゴムが現在シリーズに供給しているレギュラータイヤを使用して、空力のテストを実施。走り始めは、リヤウィングの仰角を31度に設定し、フルダウンフォースでの走行となる。塚越と石浦は、まず今回のクルマの状態を確認し、コンディションに合わせてセットアップを微調整した。その後、追走テストに入る予定だったが、セッションは開始から約35分という時点で赤旗によって中断。これは、レインボーコーナー付近に小動物が迷い込んだため。その動物が姿を消したのを確認し、セッションは午前10時42分に再開された。
この再開後、2台はまずフルダウンフォースのまま追走テストに入る。そのデータを取った後は、一旦ピットイン。リヤウィングを寝かせ、ダウンフォースを削った状態でのテストに入る。そして、セットアップの確認をした後、午前11時43分頃からはダウンフォースを減らした状態での追走テストを実施した。
このセッションでは、塚越が48周を消化し、ベストタイムは1分07秒782。石浦が39周を消化して、1分06秒654というタイムをマークしている。

2時間のインターバルを経て、2回目のセッションが始まったのは午後2時。この頃、菅生の空には若干雲が出ていたため、セッション開始時の気温は29℃、路面温度は48℃と午前中の最後よりは少しつがった。
この午後のセッションでのメインはタイヤテスト。また、石浦が乗るレッドタイガーSF19 CNには、V8サウンドを奏でるためのメインパイプとウェイストゲートパイプが装着され、音のチェックはもちろん、排気管回りに熱害が発生しないかなど、細かなテストが行われた。
タイヤに関しては、セッション開始から20分ほどの所で塚越が最初にグリーンの帯が入ったものを装着。その5分後には石浦も同様にグリーンの帯が入ったタイヤに履き替えてテストに突入した。今回は、初回の富士からこれまで3回テストしている「コンパウンドC」、オートポリスから投入された「コンパウンドE」、「コンパウンドF」と3種類のコンパウンドを「ケーシングD」と組み合わせたものを順にショートランでテスト。最後に「ケーシングD」に現在シリーズで使用中のレギュラーゴムを乗せたものをテストした。2日目には、その中から選んだタイヤをロングランすることが決まっている。
そして、タイヤテストがほぼ終了したセッション終盤には、石浦のレッドタイガーSF19 CNがエンジンマッピングを変更。さらに甲高い音を奏でながらコースを疾走する姿が見られた。
このセッションでは塚越が51周を走破して、1分06秒385というベストタイムをマーク。石浦は、54周を走破して1分06秒098というベストタイムをマークしている。両ドライバーとも、酷暑の中、ほぼ2レース分を走り切った形だ。


明けて21日(火)は、1年の中で最も昼間の時間が長い夏至。この日も宮城県南部地方は朝から好天に恵まれた。ただし、初日と比べれば、若干暑さは和らぎ、心地よい風が吹いてくるようなコンディションとなった。
2日目、最初のセッションは午前9時から午前11時までの2時間。開始時点で気温は23℃、路面温度は38℃まで上昇していた。初日は通常のレースガスを使用していたが、この日はカーボンニュートラル燃料をテスト。すでにテストした2社の製品ではなく、今回はまた新たなものが持ち込まれている。セッション序盤は、その燃料でのエンジンやマシンの状態を確認。その後は、タイヤのロングランテストに入る予定となっており、塚越がステアリングを握るホワイトタイガーSF19 CNは、セッション開始から30分ほどの時点から、まず「ケーシングD」にレギュラーゴムを乗せたタイヤで構造のロングラン。それを終えると、一旦休息時間を挟んで、レギュラータイヤでのロングランを行い、2つの違いをテストしている。一方、石浦がステアリングを握るレッドタイガーSF19 CNは、燃料のテストを行なった後、しばらくピットに停止していた。これはマシンに操作系トラブルが発生したため。そのトラブルシューティングが終わると、石浦はレギュラータイヤで再度走行を開始したが、このセッションではロングランテストに入ることができなかった。
この午前中のセッションでは、2回のロングランを行なった塚越が63周を消化し、ベストタイムは1分08秒047。トラブルで途中走れなかった石浦は30周を消化して1分07秒831というベストタイムをマークしている。


2時間のインターバルを経て、今回最後のセッションが始まったのは、午後1時。この頃になると、SUGOの空は薄雲に覆われ、涼しい風が吹いていた。夏というよりは初夏の爽やかな陽気となっている。
このセッションでは、塚越が2種類のタイヤでロングランテストを実施。「コンパウンドC」と「ケーシングD」のニュータイヤからのロングランを行なった。一方、石浦はレギュラータイヤと「コンパウンドC」の2種類でロングラン。こちらは、初日にショートランしたユーズドタイヤでの走行となっている。この最後のセッションでは、小動物が現れたため、午後2時18分から24分まで赤旗が提示される場面もあったが、それ以外は2台が淡々とロングランを続けた。塚越は61周を走破して、1分07秒806をマーク。石浦は58周を消化している。
塚越広大(白寅:White Tiger SF19 CN)

「空力に関しては、ここまで3回テストしてきて、基本的な評価は今回も余り変わらないです。ただ追走していて、ラインが交錯したり、後ろについた時、フルダウンフォースの場合は多く抜ける感じがあって、変化量は大きいですね。それに対して、ダウンフォースを減らしていった時の方が、抜ける量は少ないので、変化は少ないと思います。交差することがなければ、最終コーナーなどはある一定の距離感でちゃんと走れるなと、改めて分かりましたね。ある程度の距離があると、どちらのダウンフォースでも余り変わらないんですけど、近づいた時の変化量については違いはあると思いました。これまでのサーキットでも、ダウンフォースを減らしたからオーバーテイクが増えるのかというと、それだけではまだ難しいかなと。その感触はSUGOでも同じです。
音に関しては、僕はピットに戻っている時にちょっと聞いただけですけど、従来よりは少し甲高い音が聞こえて来ていたなと感じました。もちろん、「音がいい」って何がいいかって難しいんですけど、自分が「ああ、いい音だな」って思うのは、もう少し高音側の甲高いような乾いた音がする方向。そういう音だと「レーシングカーっぽいかな」っていうのがありますね。今後ホンダ側もテストをしていく予定ですが、それに近づけば嬉しいかなと思います。
今回のカーボンニュートラル燃料に関しては、ガソリンとの違いも余り感じることなく普通に走れた感じでした。パワーの出方とかフィーリングは現行のものにほぼ近い感じです。
タイヤについては、ここまで路面温度が上がるテストは初めてでした。ただ、これまでテストして来た中で評価が高かった構造だったりコンパウンドだったりという物は、SUGOでも良かったと思います。ここまでテストしてくる中で、新しい物はちょっとソフト目というフィーリングがあったので、路面温度が低いとコントロールタイヤよりもウォームアップが良かったり、低速でのグリップがあったんですけど、ここまで温かいとそこまで差がありませんね。ただ、それでもコントロールの方が少ししっかりしているイメージで、僕がいいと思ったものはコントロールよりも構造とコンパウンドのバランスが良かったり、そういうのはありました。ロングランもしましたけど、新しいもののグリップが落ちるとかそういうことも今の所ありませんでしたね」
石浦宏明(赤寅:Red Tiger SF19 CN)

「SUGOはリヤウィングの仰角31度の時とそこから減らした時と、そこまで近づいて走れる距離にそんなに大きな差を感じなかったというのが正直なところです。ただ、近づいた時にダウンフォースが抜ける度合いは、やっぱり31度の方が大きかったですね。後ろについて1コーナーに入ったら、急にリヤがすっぽ抜けてフラフラしたり。一気に抜けるので、その差にビックリするんです。こんなにグリップしないのかと思うんですよね。それに対して、減らしていった時には、抜けてもすごく(グリップ感が)変わるというわけでもないので、減らした時の方が追走するには走りやすいなという印象でした。追走では、馬の背、SPを走っている間に結構距離が開いて、最終コーナーに行くまでにもう離れているんですね。最終コーナーはずっと長い右コーナーで、意外に風は内側からちゃんと受けて、その距離をキープすることができるんですけど、その前で離れてしまうので、コース特性としてもちょっと近づきにくいところはあります。ただ、レースを見ていても、OTSを使ってオーバーテイクはできる。上り坂ではやっぱりパワーが効くので、現行よりちょっとでも近づいて走ることができれば、もっと効果があるのかなという風に思います。
また、昨日は音のテストをしました。今朝、外からの映像も見たんですけど、その映像以上に、乗っている方が音の違いを感じました。乗っている時は、楽器じゃないですけど、ちょっと甲高い音が右の耳だけに入ってきました。排気が右だけなので。左は静かで、その左右の差が最初は気になったんですけど、いつもより(エンジンの)高回転域を使っているような音なので、走っているうちに「お、これは速いぞ」っていうイメージがあって、クルマの速さとは合っているかなと思いました。今まで、クルマは速く走っているんですけど、音はちょっとこもっていたじゃないですか。その感じからすると、乗っていて高回転のいい音がするので、外から聞いたらどんななのかなと。でも、正直なところ、外から聞いた方がちょっと差を感じにくいのかなという風に思いました。ただ、最後に高回転で回して、レブに近いところで走ったんですけど、その時の方がより差が出ていたような感じでしたね。
今回テストした燃料に関しては、最初ドライバビリティーの部分で微調整が必要だったんですけど、合わせてもらってからは全く現行のレースガスとドライバビリティーも同じですし、パワーも同じぐらい出ていて、言われなければ違いが分からないぐらいでした。
タイヤに関しては、初日にショートランでコンパウンド3種類と構造1種類をテストしました。その中から同じ構造に、レギュラーのコンパウンド、新しいコンパウンドという2種類を横浜ゴムさんにチョイスしてもらって、2日目にロングランをしています。ロングランした2つに関して言うと、コントロールのゴムの場合には、上手く新構造を使えていました。一方、テストコンパウンドの方は、構造との相性からアンダーステアがどんどん増えていって、ラップタイムがどんどん落ちていってしまいました。構造とコンパウンド、新しいもの同士なんですけど、組み合わせによって上手く行ったり、難しかったりするっていうのが、結構明確に分かりましたね。走行後のミーティングでも、今後に向けて重点的にしっかり相性のいいものというか、使えるものを探して行こうと。次の富士テストではまた違う物も用意されるらしいので、その辺をしっかりテストしたいです。レースで実際に使うとなったら、摩耗であったり、タレであったり、ウォームアップ性であったり、色々必要になるというか、担保しなくちゃいけないものもあるじゃないですか。その辺も、そろそろ来年に向けて、本当に使うスペックでしっかり評価ができるよう絞り込んできている段階なので、そのためにも今日はすごくいい組み合わせのロングの評価ができたと思っています。ショートランでは今までと同じように、全部コントロールに対してすごく近いところにあって、ロングランになった時にちょっと差が出たので、やっぱりしっかりとロングをすることが大事だなというのが、今回のテストの結果です。あと、SUGO自体、長く負荷がかかる最終コーナーなどがあって、もともとタイヤの摩耗が厳しいコースなんですけど、テストではタイヤによって磨耗の差も出たので、それもすごく大事なデータになったと思います。レースが面白くなるようなタイヤというのはすごく必要ですし、一方で安全性も大切なので、それを両立しながら色々な要素を混ぜていかないといけないんですよね。ヨコハマさんが今回のデータを持ち帰って、次の富士では新しい物が出てくると思いますが、その時にどういう結果になるのか、今から楽しみです」
永井洋治テクニカルディレクター
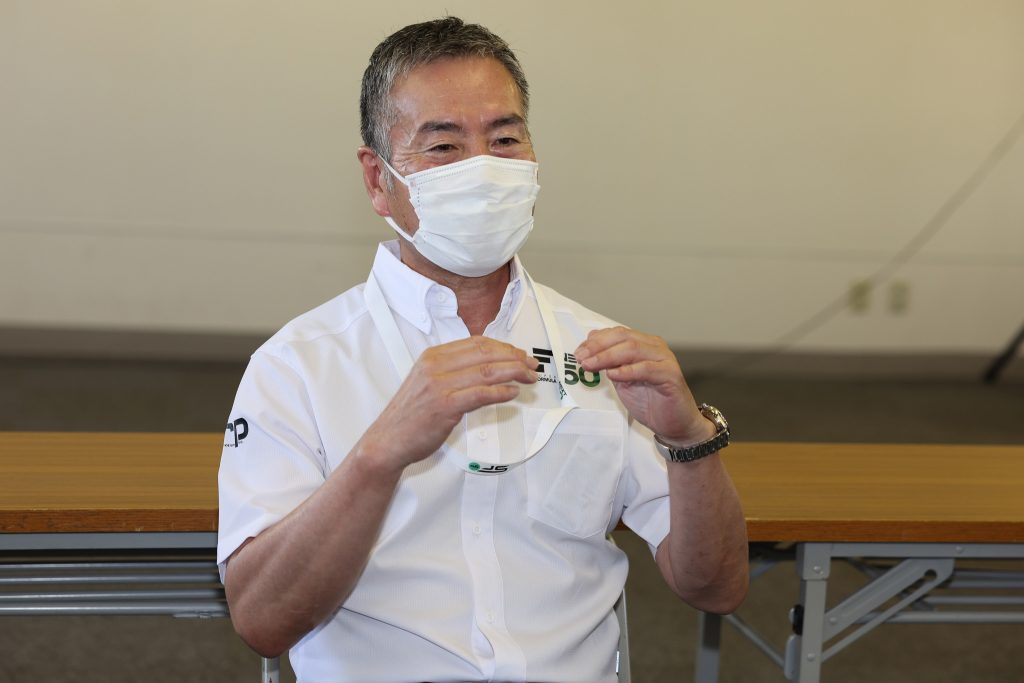
「テスト初日の大きなメニューは4つありました。まずリヤウィングの角度31度とそこから減らしての追走テストをこのSUGOでもやりました。結果で行くと、似たような感じですけれども、SUGOは追従性に関して、フルダウンフォースの時と減らした時の差がむしろ少なかったというコメントがありました。ただ、ポジションが左右に入れ替わる時には、やっぱり31度の時の方が影響が大きいというデータが出ています。あと、大きいのは絶対値。ダウンフォースを減らした時の絶対値でも、問題なく走行できるというということだったので、次の車両の絶対ダウンフォースを決めるという意味では、ほぼ色々なサーキットで確認できたというのは大きかったです。次に引き続きタイヤテストをやりました。カーボンニュートラルの素材もだいぶ煮詰まってきているんですが、このSUGOでもチェックできたというのは大きかったです。あとはBcompの試験も引き続きやっています。それから、エンジン音に関しては、TCDが主体でやっていました。それに関しては、色々な捉え方があると思いますけど、まず「できた」ということが私としては良かったと思います。実際に感度はありますので、今後チューニングすることで、ポテンシャルはまだまだ引き出せると思いますし、カーボンニュートラルを使った多気筒エンジンだったり、ダウンサイジングだったり、将来のレーシングカーの成り立ちが広がって、すごくいい試験ができたと思います。
そして2日目は3種類目の燃料のテストを行いました。会社が違うので、成分が微妙に違ったり、作り方にも少し違いがあると思います。エンジニアリング的にネガな要素は、今までのところ今回のものが一番少ないかも知れないなという感触を持ちました。次回のテストには雨を期待しています。ドライタイヤは大体絞り込めてきたんですけど、ウェットタイヤは1回もテストできていないので、そこが今最大の課題です。中でも、ウェットのウォームアップ性を試したいのですが、気温が高くなってきて試せない条件になってきているので。だから、雨が降って、少しでも路面温度が下がった状態で、富士でそのテスができれば嬉しいですね。Bcompも雨で試したいと思っていますし。また、次回からはホンダさんも音のテストをする予定なので、それにも期待しています。今回がスタートで、あとはどんどん良くなる一方なので、そのポテンシャルをどこまで引き出せるかを見るチャンスがあるのは、非常に楽しみです」
★佐々木孝博(TRD本部MS開発部部長)
写真左:右は境氏
「実際に作ったメインパイプとウェイストゲートパイプゲートパイプは、今回持ち込んだ1種類だけです。1種類を作り込んでベンチで確認して持ってきました。ただ、ベンチ室というのはどうしても聞こえる音が変わってきますし、サーキットでも皆さんが聞かれている場所によって、音が変わってくると思います。なので、ベンチとの違いというのは難しいんですけど、音を録って音響解析をし、ちゃんと狙ったところのデータが出ているということを確認して持ってきています。今回も色々な所で音は録っていますので、それをまた解析して合わせ混むというか、持ち帰って作業します。私はベンチでの音も聞いていますし、実際シミュレーションしている数値的なデータやグラフも見ているので、先入観が入ってしまっていますが、実際に走らせてみて、その領域がしっかり再現できているなという風に思いました。今後、さらにいい音にするために改善できるのは、メインパイプやウェイストゲートパイプゲートパイプ。そこから出てくる排気の量によっても音は改善されます。今日の一番最後のアウティングに関しては、ホンダの佐伯さんからの熱いリクエストがありまして(笑)、(ターボブーストを下げて)ウェイストゲートパイプゲート側から出す排気量を増やして走りました。そうすると、やはり出てくる音域は、より高回転側にズレたかなと思います。いい音を作るためには、こういう手段もあるよねっていうことは分かりましたし、これによってホンダさんとも協力して音作りをしていければと思います。最終的には共通部品でいい音で走れればいいのかなと思っていますし、次回ホンダさんがテストされるのであれば、また情報共有しながらやらせていただければなと思いました」
★境真也(TRD本部MS開発部パワトレ開発室第1開発グループ上級主任)
「今回、シミュレーションもして、設計をして、評価もしました。直4をV8の音にするという企画があり、まず4発の音を8回聞こえるようにという所でシミュレーションを行なって、それをベンチで試験して持ってきました。ベンチでは、ベースの物とパーツを変えて、同じ回転数で比較できますが、今回持ち込んだものを使用した時に、明らかに甲高い音が出て、高回転の違いというものは分かりました。サーキットで聞くと、シチュエーションが色々ありますので、同一の比較がなかなかできないんですけど、データを後で確認して、ちゃんと効果があったかどうか。また、さらにいい音になるようにというところをやっていきたいと思います。今回フォーミュラカーには余り似つかわしくないようなものを作ったんですけど、(エンジンの)性能としてはそんなに落ちることなく試験ができました。今回は、(メインパイプ)の長さが肝なんですが、あの長さで例えばテールから出せることができればと個人的には思っています。熱に関してはかなり心配しましたが、かなり事前の処置を色々やったことで今回は大丈夫でした」


